冬の上場企業・上場会社情報
冬のスポーツで活躍している「上場企業」の実業団チーム/ホームメイト
冬に楽しむことができるスポーツ。そこで活躍している選手がいます。活躍している選手はプロの選手ばかりではありません。実業団のチームで活躍する選手達もいるのです。実業団チームとは企業に在籍し、会社の運動部として活動する人達のことです。「上場企業」では、会社のイメージアップや広告塔として実業団チームを発足している企業も。そこで、冬のスポーツで活躍する実業団チームをご紹介します。
冬の駅伝に出場する「上場企業」の実業団
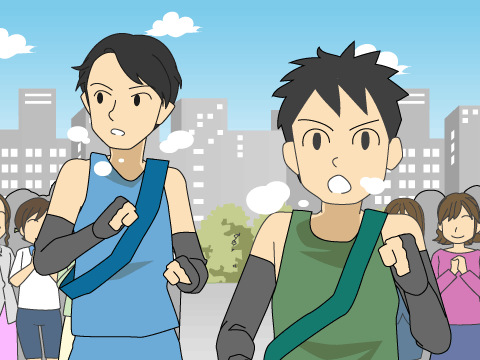
冬のスポーツとして代表的なものとして思い浮かべるのが「駅伝」。その中でも1月1日に開催される「ニューイヤー駅伝」はお正月の風物詩ではないでしょうか。正式には「全日本実業団駅伝」と呼び、開催回数60回以上の歴史と伝統があり、日本各地にある実業団チームが集まって「駅伝」の日本一を競います。毎年各地区の予選を勝ち上がった37チームが出場。中には、出場枠を巡る熾烈な争いを勝ち抜き、「ニューイヤー駅伝」の常連と言われる「上場企業」の実業団チームがあります。日本の自動車メーカーでおなじみの「Honda」は、33年連続で過去34回出場を果たす名実ともに常連チーム。「Honda」の陸上部は1971年(昭和46年)に創部されました。現在所属する選手で活躍が目立つのは、「リオデジャネイロオリンピック」の陸上競技選手団にも選ばれた設楽悠太氏、石川末廣氏です。優勝歴こそないものの、毎年上位に食い込む接戦を見せてくれます。ここ10年で一気に実力を伸ばしてきた「日清食品グループ」も、「実業団駅伝」で活躍する企業のひとつです。1995年(平成7年)に陸上部発足。翌年には同部所属の実井謙二郎氏が「アトランタオリンピック」の男子マラソンに出場するなど、有能な選手が集まる団体となっています。2010年大会では初優勝を飾り、翌年も3位入賞、2012年にも優勝を獲得しました。22年連続出場の名に恥じない実績を積んでいます。
「スキー競技」の実業団を持つ「上場企業」
冬のオリンピック競技でも人気の高い「スキー競技」。ニュースやスポーツ番組などで中継されることもあり、冬のスポーツとして広く認知されています。日本国内にとどまらず、世界で活躍する「スキー競技」の実業団を持つ「上場企業」をご紹介します。総合建設会社として建設工事や都市開発、またホテルや施設などの経営までを行なう「北野建設株式会社」です。「北野建設スキー部」は1971年(昭和46年)に創設。翌年には札幌オリンピックに出場しています。過去在籍した有名な選手は、「女子モーグル」として5度の冬季オリンピックに出場した上村愛子女史。惜しくもメダルには届きませんでしたが、すべての大会で入賞を果たしました。そののち、「ノルディック複合」で世界のトップに立っていた荻原健司氏がゼネラルマネジャーを就任し、チームをけん引しています。牛乳や乳製品など身近な食品を多く扱う「雪印メグミルク」のスキー部は古く、1946年(昭和21年)に創立。「長野オリンピック」では、スキージャンプの団体として、「雪印メグミルクスキー部」から3名が出場します。この大舞台で見事金メダルを獲得し、日本中を感動で包みました。当時団体のメンバーだった原田雅彦氏は、スキー部の監督を務めています。
ラグビーの冬大会で活躍する「上場企業」
社会人選手などが所属する実業団のラグビーで有名な大会が「トップリーグ」。日本の最高峰リーグとされ、毎年8月頃に開幕し、2月頃に閉幕します。ラグビーは夏から活発に行なわれていますが、冬のイメージが強いスポーツ。これは、「全国高校ラグビー大会」をはじめ、トーナメントやリーグ戦など多くのラグビー選手権が12月から3月にかけて開催されていることや、花園で開催される高校の「全国大会」が12月~1月であることから。「上場企業」の実業団チームとして有名なのは、洗濯機や冷蔵庫、エアコンなど、家庭用家電メーカーの「パナソニック株式会社」が所有するラグビーチームの「ワイルドナイツ」。1960年(昭和35年)に創部し、発足してわずか数年で関東社会人リーグ優勝を果たしました。2016年(平成28年)の「トップリーグ」では、堀江翔太氏がMVPを獲得しています。2017年(平成29)年の「トップリーグ」では3位でした。大手鉄鋼メーカーである「神戸製鋼所」のラグビー部、「コベルコスティーラーズ」も有名で、創部したのは1928年(昭和3年)。「コベルコスティーラーズ」は日本の実業団ラグビーの中でも古株的存在です。1988年(昭和63年)開催の日本選手権で初優勝を飾ると、そこから7連覇を果たします。日本選手権での優勝回数は9回と歴代最多を記録。「トップリーグ」や「全国社会人大会」でも優勝経験のある、名門のラグビーチームです。



上場企業や優良企業を目指す就職活動中の学生にとっての冬は、「内定がもらえた人」と「内定がまだもらえていない人」とに明暗が分かれる時期です。しかし、企業には冬期採用を取り入れている企業もあり、内定獲得を諦めるにはまだ早いと言えます。また、就職活動をまだ始めていない学生も冬休みを利用して企業研究などを行なっておくことが大切です。企業研究は、いざ就職活動をスタートさせようというときにとても役立ちます。
学生が希望する働きたい企業とは

就職活動を行なう大学生を対象にして調べる「就職したい企業」のランキング。これは就職情報などを提供する企業から毎年発表されており、その時代の景気や世相を反映した内容となっています。例えば2016年(平成28年)度に発表されたランキングでは1位が地方公務員、2位が国家公務員、3位と5位が航空業界となっており、名前が挙がっている上場企業にはIT系企業も少なくありません。しかし2010年(平成22年)のランキングは、大手鉄道会社やメガバンクが上位を占めているにもかかわらず、2016年(平成28年)のランキングでは鉄道会社もメガバンクも10位以下にとどまるなど、時代によって人気企業が変化しているのが分かります。どの時代にも上場している有名企業、優良企業が上位を占めることには変わりませんが、就職したい会社というのは、その時代の若者の考えや世相が強く反映されていると言えるでしょう。
なお、就職活動そのものは昔からありますが、過去と現在の就職活動には大きな違いが見られます。まずはインターネットを用いたスピーディーな就職活動。これは学生にとっては多くの企業にアプローチができ、企業側にはより多くの人材と接点が持てるメリットがあります。最近では企業説明をインターネットで行なう企業もあり、エントリーそのものをインターネット上でするというのが一般的となってきました。また、採用にあたって企業側が行なう面接基準も今と昔では変化しています。昔はその企業に対して、どれだけ適正な人物であるかを主な基準として選考していたのですが、現在では適正よりもコミュニケーション能力の高さやポテンシャルの高さを選考基準にしている企業が増えています。これには企業が多様な分野に進出していることが大きな理由であるとされ、1企業1業態という昔の企業形態が減少したため、様々な職務に順応できる人材が求められています。
エンプロイヤーブランディング
「エンプロイヤーブランディング」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?これは、アメリカで注目され始めた新しい概念で、“企業の人材採用や確保にあたって職場が魅力的であることをアピールするための戦略や方法”を指す言葉です。エンプロイヤーブランディングが意識され始めたのは、学生がよく利用しているツイッターやインスタグラムといった、ソーシャルメディアの発展が背景にあります。
企業側が職場環境や会社の雰囲気などをアピールすることでソーシャルメディアは手軽かつ効果的なPRツールとなったのです。以前は入社してからしか分からなかった職場の雰囲気や文化、社風などもソーシャルメディアを通して発信できるようになりました。企業がユーザーとコミュニケーションを取り、考え方の発表をソーシャルメディアで行なうことで、企業とユーザーとの距離が近づいたのです。
上場企業の中にはエンプロイヤーブランディングと併せてソーシャルネットワークを使った採用活動である“ソーシャルリクルーティング”を取り入れる企業もあります。これらをうまく利用することで、企業は最終的に自社にマッチした人材の確保が可能となるのです。
こういった取り組みは日本でもIT関連の企業を中心に浸透しつつあり、就職活動中に志望する企業を、ソーシャルメディアでフォローしておくのも効果的だと言えるでしょう。
冬採用を行なう企業
就職活動中の学生にとって身近なワードに、「春採用」「夏採用」「秋採用」「冬採用」というものがあります。一般的に大学生の採用は「春採用」がメインの企業が大半ですが、12月から3月の期間を目安に採用を行なう「冬採用」を取り入れている企業も少なくありません。冬採用を行なっている企業の多くは、競合他社のある大手企業の他、専門分野に特化している中堅企業も見られます。事業拡大を図るための人材募集というケースもあるため、将来性のある企業が見つかるかもしれません。また、冬採用を定期化している企業も少なからず見られるので、過去の採用実績などを調べて情報を収集することが肝心です。
年が改まると、上場企業では様々な行事ごとがあります。こうした行事ごとから、伝統や企業風土を垣間見ることができます。また、組織体制や事業活動などをまとめたリポート・報告書では、企業としての社会的影響をうかがい知ることができます。
初荷
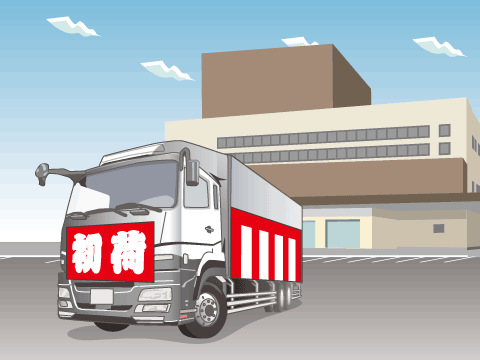
新しい年が明け、正月休みが終わると新しい年度がスタートします。百貨店やメーカー直営店などでは初売りを実施し、多くのお客を集めますが、製造メーカーの場合は初売りの代わりに初荷を行ないます。これは、工場や倉庫などの物流拠点から販売店に向けて、今年初めて製品を出荷することです。初荷は企業と取引先にとって縁起物としており、年末に注文を取って、年始に配達・納品することが恒例でした。最近はあまり見られなくなりましたが、かつてはトラックの荷台に紅白の旗やのぼりを付けて、販売店に納品する企業も多くありました。
また、初荷を取引先に納めることで、それが新年の挨拶にもなります。また、製品を納めなくても、仕事始めに取引先に挨拶をする年始回りは、ほとんどの企業の営業マンには必須事項です。
企業によっては営業マンだけでなく責任者なども同行して、取引先と和やかに挨拶を交わしながらコミュニケーションを図るところもあり、ビジネスとしての繋がりを強くします。
取引先と元気よく笑顔で挨拶を交わして、順調なスタートを切りたいですね。
社内成人式
1月第2月曜日は成人の日で、20歳を迎えた新成人を祝う日です。一般的に、学区や自治区ごとに新成人を集めて、祝賀式典などが開かれますが、企業によって自主的に社内成人式を実施するところも多いです。その年に20歳になった従業員を一堂に集めて、社長がお祝いのメッセージを述べ、記念品を渡したり、記念撮影をしたあとに食事会を開いたりと、いろいろな社内成人式が行なわれています。企業規模によって式典の内容は異なり、グループ会社や生産拠点などに分かれて実施する企業もあります。
こうした社内成人式では、新成人は着飾ることなく、通常の制服や私服で出席するのが慣例で、仰々しさがないだけ自然な振る舞いができます。それでも、ひとつの節目を迎えることから新成人たちも心を引き締めるように式典に臨み、決意を新たにしていることでしょう。新成人たちには、社会からも社内からも大きな期待が寄せられます。
CSRリポート
上場企業では、年が改まると年度末に向けての決算準備が着々と行なわれます。収支などの経理面だけでなく、製品品質、職場環境、労働安全衛生、環境対応など、1年を通して実施してきた企業活動の総括も行なわれます。こうした活動を消費者や取引業者、投資家など、その企業にかかわりを持つステークホルダー(企業と利害関係を有する者)に公開するのが「CSRレポート」、または「CSR報告書」です。
「CSR」とは、「Corporate Social Responsibility」の略で、「企業の社会的責任」と訳されます。上場企業などの大企業は、企業活動自体が社会に与える影響が大きいことから、注目度も高くなります。そのため、利益の追求だけでなく、その影響力に責任を持つことを意味します。企業に求められる社会的責任は、財務状況の透明化、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメントと言った健全経営による社会的信頼の確保と、労働問題や環境問題など、企業が自主的に取り組む活動の2つの側面があります。「CSRリポート」では、こうした企業の実状や取り組み内容を項目ごとに紹介しています。
また、地域社会との交流や社員教育、ワークライフバランス、障がい者雇用など、地域活動や労務問題も広く公開し、社会での役割を示しています。このリポートや報告書により、企業の姿勢や目指す方向性が分かるので、興味のある企業のものは目を通しておくとよいでしょう。
企業にとっての冬は、年末年始や決算前の準備など何かと忙しい時期となります。そんな中で、12月22日は労働組合法が制定された記念日となっています。この法律のおかげで、企業で働く人の生活や雇用は労働組合によって守られることになりました。
労働組合法制定記念日(12月22日)
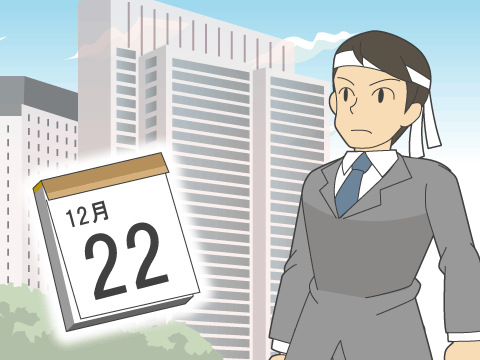
ほとんどの企業において、労働者の生活や職場の安全を守るために労働組合が結成されています。今では労使が激しく対決することはほとんどありませんが、かつては賃上げや休日の確保をめぐってストライキやデモなどが繰り広げられた時代もありました。こうした労働者の団結権、団体交渉権、労働争議などを保証する「労働組合法」が制定されたのが1945年12月22日で、翌1946年3月1日に施行されました。
労働組合法は、労働基準法、労働関係調整法と並んで「労働三法」と呼ばれており、労働者の地位の保護や向上を保証しています。
労働組合の歴史は、18世紀にイギリスで産業革命が起こった時代にまでさかのぼります。産業革命によって製造分野の工業化が発達し、それまで熟練工の仕事が素人でもできるようになり、女性や児童をはじめ農民や移民なども労働者として労働市場に参加しました。これにより、非熟練労働者たちが自主的に組織を作り労働組合の結成に大きな足跡を残しました。日本における最初の労働組合は、1897年に結成された職工義友会を母体にした労働組合期成会です。この団体は、各地で職業別組合を結成するように演説会を開いて呼びかけ、その後、鉄工組合、日本鉄道矯正会、活版工組合が誕生しました。ヨーロッパでは、産業や地域、職種になどによって労働組合が構成されていますが、日本の場合は、企業やそのグループ企業の従業員によって構成されています。さらに産業別で連合体が組織され、各産業の主力企業の労働組合が連合体の主導権を握っているケースが多いとされています。
労働組合の役割
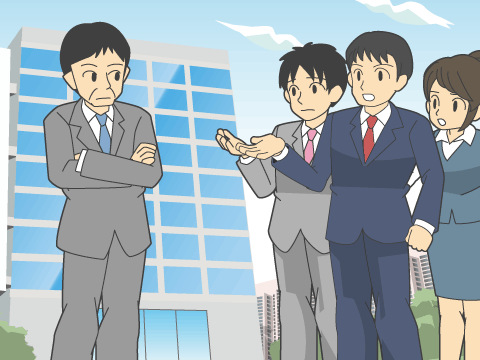
労働組合は、憲法などによって守られています。これは働く人の権利として法律で定められており、会社側は労働組合の結成や活動を妨げることはできません。労働組合が組合員のために果たす主な役割としては、①労働条件の維持・向上、②雇用の確保、③相互扶助があります。
労働条件の維持・向上では、働く人の生活は、労働に対する対価である賃金で支えられています。賃金に不満や不合理があっても、一人で会社と交渉するのは困難ですが、労働組合であれば、立場の弱い労働者の意見や要求を会社側に交渉できます。
一方、②雇用の確保は、労働組合の存在意義でもあり、会社側の不当な解雇を抑止するチェック機能を持っています。業績に合わせて会社側が無計画に採用を増やしたり、人員を整理したりしないよう、労働組合では経営情報を収集し、会社の採用計画や人材登用についてチェックします。これによって組合員の生活と雇用を守っています。
また、③相互扶助は、労働組合として主体性を持ち、共済活動などを通じて働く人たちの団結と生活の安定・向上を図るものです。労働組合は労働条件や維持・向上を目的にしていますが、最終的には労働者の幸福をより具体化して拡大することにあります。その一環として、各種共済制度やサポート制度を設けて、労働者の生活を支援したり、働く人同士が仲間意識を持てるような取り組みをしたりして、組合活動を円滑化しています。
最近では、労働者側と企業側が意見を交換し合いながら、それぞれの立場を尊重した「労使協調」を掲げるところが多くなっています。これは労働組合が結成された時代と比べて、賃金や休日などが安定してきていることが挙げられます。また、労働契約法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法など、労働者を保護する法律も数多く制定され、憲法である程度守られるようになったことも考えられます。このため、労働組合の役割や活動範囲も形的には縮小されたように思えますが、「労働者の幸福」は時代によって変化するため、組合活動も時代に即したものが求められています。









