 農林業・水産業
農林業・水産業
「農林業・水産業」を事業とする上場企業・上場会社や優良企業をお探しの方は、ビッグカンパニーにお任せください!
「ビッグカンパニー」では、日本全国の「農林業・水産業」を事業とする上場企業・上場会社や優良企業の情報をまとめました。検索方法もカンタン!都道府県名から地域を選んでお探しの「農林業・水産業」を事業とする上場企業・上場会社や優良企業が見つかります!
農林業・水産業とは
食料、木材、繊維といった原材料を生み出す「農林業・水産業」は、人類が太古の昔から連綿と営み続けてきた、最も古い産業と言えます。しかし、現代社会では労働環境の問題と収益性の低さなどから慢性的な人手不足に陥っているのが実情。生産現場の効率化及び近代化が急務となっていました。
農林業・水産業は、人間が生きていくためになくてはならない産業であり、将来にわたって持続可能な産業を目指す新たな取り組みとして、情報技術の活用が進められています。
目次
農林業・水産業の概要
農林業・水産業の業界規模
産業分類上、1次産業にあたる農林業・水産業には、大きく分けて、米、野菜、果物、花卉(かき)などの農作物を栽培・収穫する「農業」、牛、豚、鶏などの家畜を飼育して食肉及び乳製品、鶏卵の生産をする「畜産業」、山林の手入れを行いながら木材などを産出する「林業」、魚介類の漁撈(ぎょろう:事業として漁を行うこと)と養殖を行う「漁業」、水産資源を利用して加工食品などを製造する「水産加工業」があります。
農林業・水産業の規模としては、主要11社の売上高合計が約2兆円で、伸び率は4%ほど。他業界と比べてもそれほど大きくはありませんが、人間が生きるうえで欠かすことのできない食を支える分野だけに、天候及び自然災害などに左右される側面を割り引いて考えたとしても、比較的安定した業界であるとされています。
ただし、水産業に関しては、2001~2018年(平成13~30年)度の17年間で、魚介類の一人当たりの年間消費量が4割も減少。年々深刻化する日本人の「魚食離れ」に対し、骨抜きをした魚、簡単に調理できるミールキットの商品化など、水産加工会社による利用促進の工夫が続けられています。
就業人口の減少と高齢化

農林水産省の統計によれば、農林業の就業人口はかねてより減少傾向が続き、2020年(令和2年)の時点で、20年前の約60%までに減少。水産業でも同様の状況で、2003~2017年(平成15~29年)の14年間で約33%も就業人口が減少しました。
就業人口減少の原因の一端は、後継者不足と高齢化です。かつては代々屋敷、土地とともに家業として農業を受け継いでいましたが、過重な労働のわりに収入の保障がないことから、親世代が子への継承を望まなくなったこと、同時に子世代も家に縛られることなく自ら進路を選択するようになったことが背景にあると指摘されています。
そこで国及び地方自治体では、農業に関心を持つ人の地方移住と新規就農に対し、手厚い支援策を導入。「Iターン就農」を促進して人材の確保に努めています。
さらに、安定した収益の確保で、若い世代が農業に希望を描けるようにするため、農林業・水産業の「6次産業化」にも取り組んできました。
6次産業化とは、1次産業から3次産業まで網羅した産業という意味であり、本来1次産業である農林・水産業の生産者自らが、商品開発から製造及び販売まで担うことで、付加価値の高い産業を目指すという考え方です。農家に宿泊して、農業体験をする「アグリツーリズム」などの観光業化もその一環とされています。
農林業・水産業の現状と課題
日本の食料自給率
自国で消費する食料を、どの程度国産で賄っているかを示す割合が「食料自給率」です。日本政府は2020年(令和2年)に、10年後の2030年(令和12年)までに食料自給率をカロリーベースで45%、生産額ベースで75%に引き上げる目標を立てています。
1961年(昭和36年)時点で78%とされていた日本の食料自給率は下落の一途をたどり、2010年(平成22年)には、ついにカロリーベースで40%を割り込みました。
これは先進国の中でも最低水準。例えば、2019年(平成31年/令和元年)のデータを見ると、カナダの233%を筆頭に、オーストラリア169%、フランス131%、アメリカ121%と高い食料自給率を示し、ドイツ、スペイン、スウェーデンでも80%を上回っています。
食料の多くを輸入に頼っているということは、輸入相手国で災害、紛争が起きた際に、食糧を確保できなくなるなど、国民の暮らしがおびやかされる事態になりかねないのです。
実際に2022年(令和4年)にロシアがウクライナへ侵攻すると、小麦の輸出がストップし、日本にも大きな影響が及びました。世界情勢が不安定さを増す中、日本の食料自給率は30%台から回復する兆しはなく、重大な政治課題のひとつなのです。
新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルスの感染拡大は、日本の農林業・水産業にも大きなダメージを与えました。2020年(令和2年)4月に発出された最初の緊急事態宣言により、外食産業及び学校給食への出荷が停止されたことで、余った収穫物の大量廃棄、単価及び卸売価格の下落、労働力不足、資材調達不安など、経営危機に陥る事業者も少なくありませんでした。
農林水産省では、経営継続補助金、販売促進支援、「Go To Eatキャンペーン」などの支援策を講じてきましたが、感染の収束が見通せない中で、回復に向けた波に乗り切れない状況が続いています。
一方で、オンラインで直接消費者と取引できる「産地直送サイト」を活用して、新たな販売チャネルを獲得するなど、自ら活路を切り開いたケースもあったことは、これからの農林業・水産業におけるヒントとなりました。
農林業・水産業の最新トピック
農林業・水産業では、「スマート農業」、「スマート林業」、「スマート水産業」と銘打って、最先端のICT(情報通信技術)、AI(人工知能)、ロボット技術などを生産現場に活かす取り組みが進められています。
これは作業の自動化、情報共有の簡易化、データの活用で、現場の様々な課題を解決しようというもの。
例えば農業では、AIとドローンを駆使した画像解析で害虫の位置を特定し、農薬散布を必要最小限としたり、IoTセンサー(物理的変化を測定)と収穫ロボットなどを組み合わせたモニタリング装置で、トマトの収穫予測を行ったりするなど、労働力の軽減、熟練技術の共有が図られています。
林業においても、ドローンによる森林資源量の調査、スマートフォンを活用した木材検収システムなどで、作業時間や経費の削減が実現。水産業では衛星情報、AIを活用した沖合の漁場予測、養殖場でのAIによる自動給餌システムなど、経験と勘に代わるデータの活用に力を入れています。
いずれの取り組みも、まだ始まったばかりであり、今後、持続可能な農林業・水産業を目指す切り札となるには導入コスト、インフラ面の整備など数多くの課題解決が必要です。
農林業・水産業の企業一覧
マルハニチロ

「マルハニチロ」は、山口県で創業した「マルハ株式会社」と北海道の「株式会社ニチロ」が、2014年(平成26年)に合併して誕生。
現在は「マルハニチロ」のブランド名で冷凍食品、缶詰、レトルト食品、サプリメント、介護食品など幅広く商品展開をし、食品業界全体でもトップ5に名を連ねています。
アメリカ、中国、タイ、ニュージーランドに拠点を置き、海外進出にも積極的。2016年(平成28年)には完全養殖のクロマグロの本格出荷も開始した他、温暖化対策、海洋資源の保全、海洋プラスチックの問題にも取り組んでいます。
| 会社名 | 所在地 | 市場区分 |
|---|---|---|
| マルハニチロ株式会社 | 東京都江東区豊洲3-2-20豊洲フロント | プライム |
ニッスイ
「ニッスイ」の前身は、1911年(明治44年)創業の「日本水産」(にっぽんすいさん)です。水産事業、加工事業、医薬品事業、物流事業、造船事業などを手掛け、世界各地の水産会社を買収するなど世界進出にも積極的で、マルハニチロに次ぐ規模を誇っています。
2019年(平成31年/令和元年)には、日本初となる「マサバ循環式陸上養殖」の共同開発に着手。寄生虫、魚病のリスクを低減する環境にやさしい養殖技術として期待が集まっています。
2022年(令和4年)に、「まだ見ぬ、食の力を。」を新スローガンに制定し、現社名に変更しました。
| 会社名 | 所在地 | 市場区分 |
|---|---|---|
| 株式会社ニッスイ | 東京都港区西新橋1-3-1 | プライム |
ホクト
「ホクト」の創業は1964年(昭和39年)。元々は包装資材の会社として設立されましたが、きのこを栽培するポリプロピレン製容器の製造を開始したことが契機となり、きのこ栽培用資材のトップメーカーに上り詰めます。
1983年(昭和58年)には「きのこ総合研究所」を設立し、食用きのこの新品種を次々に開発。研究から生産・販売まで一貫して取り組む、きのこ総合企業に成長しました。世界的な日本食ブームを追い風に、アメリカ、マレーシア、台湾にも生産販売の拠点を設けています。
| 会社名 | 所在地 | 市場区分 |
|---|---|---|
| ホクト株式会社 | 長野県長野市大字南堀138-1 | プライム |
まとめ
1955年(昭和30年)から約20年近く、年平均10%前後の経済成長を遂げた日本。地方の若い労働力が集団就職で都市へ移住し、農林業・水産業の後継者問題が注目されるようになったのもこの時代でした。
それから半世紀が経過しましたが、依然として農林業・水産業における後継者不足に解決の糸口は見えません。そこで現在、農林業・水産業の現場で注目を集めているのがICTを活用した新たな取り組みです。人類史上最も古い産業と最新テクノロジーの融合が描き出す未来の姿に、期待が寄せられています。
上場企業・上場会社の
基本情報・知識
目次
上場企業の基礎知識
- 上場企業の条件や証券について
- 証券コードで見る上場企業の分類
有名な上場企業
- 日本の大型上場
- インターネット・バブルで上場した企業
世界の上場企業
- アメリカの上場企業(IT系)
- 様々なジャンルのアメリカの上場企業
- 新興国の上場企業
日本の上場企業
- 自動車関連上場企業
- 小売・銀行関連上場企業
- 水産関連上場企業
- 不動産関連上場企業
- サービス関連上場企業
- 食品関連上場企業
- 薬品関連企業
株式投資の基礎知識
- 証券について知る
- 株式投資を知る
資産運用の進め方
- 投資タイプの考察
- 証券会社の選び方
- 資産運用のコツ
- 世界の主な株価指数
様々な金融商品
- 投資信託運用のコツ
- 外国為替証拠金取引の概要
- 公社債の仕組みと概要
- 不正取引を知る
以下の都道府県をクリックして上場企業・上場会社・優良企業を検索してください。
 「上場企業/農林業・水産業」名を入力して探す
「上場企業/農林業・水産業」名を入力して探す
関連情報リンク集
上場企業・上場会社に関連する省庁サイトです。
法律や制度の確認、統計データの取得など、情報収集にご利用ください。
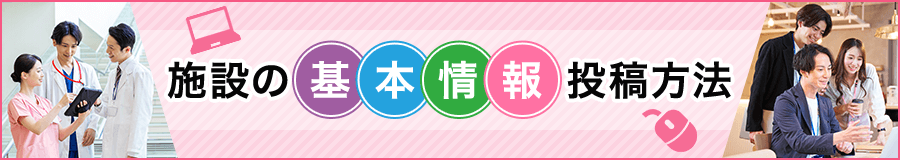
投稿をお待ちしております。



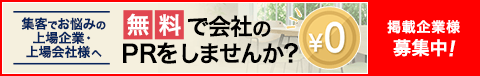

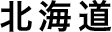

















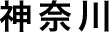
















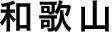











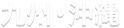






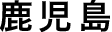

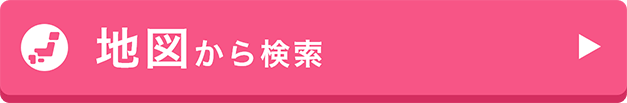
























 SNS公式アカウント
SNS公式アカウント

